「グノーブル 入塾テスト 対策」で検索している方はきっと、
- うちの子、今の学力で受かるレベルなのか?
- 全統小(全国統一小学生テスト)と比べてどれくらい難しい?
- 実際に合格したご家庭はどんな準備をしていたの?
このあたりが気になっているのではないでしょうか。
この記事では、
小3長男がグノーブル入塾テストを受けて合格した実体験と、
各種情報サイトの内容を組み合わせて、
- 小3グノーブル入塾テストの内容・難易度
- 全統小との比較・合格ラインの目安
- 実際にやっておいて良かった具体的な対策
(全統小・チャレンジタッチ・RISU算数・考える力プラスの活用)
をまとめます。
なお、グノーブルの授業の雰囲気やクラスの人数、教材の特徴など
「塾そのもの」について知りたい方は、先にこちらの【グノーブル説明会レポ】も読んでおくとイメージがつきやすいと思います。
→ グノーブル説明会レポ|少人数クラス・教材・入塾テスト前に知っておきたいこと
グノーブル入塾テスト(小3)の概要
まずは、テストの全体像をざっくり押さえておきましょう。
科目・配点・形式
- 対象:小3
- 科目:算数・国語の2科目
- 配点:各100点、合計200点満点
出題形式はマークシートではなく、自分で書いて答える“記述寄り”のテストです。
出題傾向(小3の例)
ブログ・塾記事などを総合すると、小3入塾テストの傾向はおおよそ次の通りです。
算数
- 4〜5桁の整数の四則計算、単位換算などの基本計算
- 文章題(和差・倍・単位あたり・時間・速さの入り口など)
- 場合の数、平面図形・立体図形、条件整理などの思考力問題
国語
- 小2〜小3レベルの漢字+ことばの知識(同音異義語・熟語など)
- 文章量のある長文読解
- 抜き出し・選択だけでなく、自分の言葉で書かせる記述問題
特徴的なのは、
**「教科書レベルを超えた“考えさせる問題”が必ず混ざっている」**という点です。
難易度イメージ:全統小より一段階“重い”
わが家の長男は、グノーブルを受ける前から全国統一小学生テスト(全統小)を毎回受験していました。
そのうえでの体感としては、
「全統小より、グノーブル入塾テストの方が一段階重い」
という印象です。
そう感じた理由
- 時間密度が高い
- 問題量が多く、処理スピードも必要。
- 初見の思考力問題が混ざる
- 「見たことあるパターン」だけでは対応しきれない。
- 記述の比重が高め
- 国語で、自分の言葉で書かせる問題があり、普段から書き慣れていないと時間を取られる。
実際、小3入室テストの平均点は2科で90〜110点程度という記録もあり、
「受ければほとんど受かる」ようなテストではありません。
合格ラインと、どのくらい取れていれば安心か
合格ライン:200点満点中「75点以上」で合格
わが家の長男が受験した回では、
- 合格点:200点満点中75点以上
という基準でした(グノーブル側の案内による)。
実際に、長男もこのラインを上回る点数で合格しています。
※合格ラインは回や校舎によって多少変動する可能性があります。
全統小との比較で見る「合格の目安」
体感+情報サイトを踏まえて、ざっくりとした目安を言うと、
全統小で“だいたい平均点以上”(偏差値50以上)を取れている子なら、
グノーブル入塾テストも十分合格が狙える
という印象です。
ただし、ここで効いてくるのが**「テスト慣れ」**です。
グノーブルで落ちるパターンは「実力不足」より「テスト慣れ不足」
実感として:テスト慣れしていないと落ちやすい
わが家の長男は、
- 全統小を継続的に受けていた
- 学校外でのテスト環境に、ある程度慣れていた
という状態で入塾テストに臨みました。
一方で、ネット上の体験談を見ていると、
- 学校以外でのテストがほぼ初めて
- 時間配分を全く意識していなかった
というケースだと、学力があっても失敗しやすいと感じます。
わが家がやっていて良かった「テスト慣れ」対策
- 全統小を毎回受ける
- 受けっぱなしではなく、
- どのあたりで時間が足りなくなったか
- ケアレスミスはどこか
を親子で軽く振り返る
- 「全部解けなくてもいい。できる問題を落とさない方が大事」という声かけをしておく
これだけでも、
「テスト」というイベント自体への心理的ハードルはかなり下がります。
実際にやっていた家庭学習と、グノーブル対策としての相性
ここからは、わが家の具体例です。
長男が普段やっているのは、
- チャレンジタッチ
- RISU算数
- 進研ゼミの考える力・プラス講座
この3つの組み合わせでした。
それぞれ、グノーブル入塾テストとの相性はかなり良かったと感じています。
チャレンジタッチ:基礎・標準レベルの土台固め
チャレンジタッチでは、
- 学校内容+αレベルの計算・漢字・文章題
- ハイレベル問題で、「ちょっとひねった問題」
などがバランスよく出るので、
「基本問題で取りこぼさない力」
をつけるのにちょうど良かったです。
グノーブルの算数では、
計算と小問だけで55〜60点分ほどある回もあると言われており、ここを落とさないことが非常に重要です。
RISU算数:思考力・図形・場合の数に強くなる
RISU算数では、
- 図形・場合の数・論理系の問題
- 小4以降で習う単元の入り口
にもタブレット上で触れることができます。
グノーブルの算数後半で出てくる、
- 表や図を書いて整理する問題
- パズル的な論理問題
と相性が良く、
「あ、こういう系の問題、見たことある」という安心感につながりました。
考える力プラス講座:1問をじっくり考える練習に
考える力プラスは、
- 条件整理が必要な算数
- 読む量の多い国語問題
など、**“テスト後半に出てきそうな問題”**に近いタイプの問題が多いです。
ここで意識していたのは、
- 全部完璧に解かせようとしない
- とりあえず図にしてみる/線を引いてみる、という最初の一歩を大事にする
というスタンスです。
科目別のポイント対策
算数:前半で確実に点を取り、後半に時間を残す
1. 基本計算は「反射レベル」まで
- 四則混合
- 単位換算
- 簡単な文章題
このあたりは、考え込まずにサクサク解けるレベルまで仕上げるのがおすすめです。
2. 思考力問題は「触れたことがある」だけでも違う
- 場合の数
- 図形の切り口・面積
- 表・図で整理する問題
これらは、最初から解けなくてOK。
**「こういうタイプの問題、見たことある」**状態まで持っていけると、本番での心理的な負担がぐっと下がります。
国語:読解量+記述への抵抗を減らす
1. まずは「読む量」を増やす
長男の場合、
- 漫画(ワンピース・鬼滅の刃など)
- ポケモンの図鑑や攻略本
- チャレンジタッチの読解問題や、収録されている本
- 読売KODOMO新聞
などで、日常的に文章を読む量がありました。
グノーブルの国語は、学校より長め・内容も少し抽象的な文章が出ることが多いので、
日頃から「読むこと」への抵抗がないとかなりしんどいです。
2. 記述は“枠を埋める練習”から
入塾テストでは、記述問題の配点が高めと言われています。
いきなり模範解答レベルを目指すのではなく、
- まずは何かしら書いて枠を埋める
- 親がそれを読んで、
- 主語が抜けていないか
- 設問の聞かれ方に答えているか
だけチェックする
といった**“部分点の取り方”**に慣れておくと良いです。
当日のメンタル&親の声かけも大事
持ち物まわり
- いつも使っているえんぴつ・消しゴム
- 子どもが見慣れている時計
- 終了後にすぐ渡せるおやつ・飲み物
「いつもの道具」があるだけで、子どもは安心します。
親からの声かけ
テスト前に意識していたのは、
- 「全部解けなくて大丈夫」
- 「わかる問題から解いてね」
- 「わからない問題に時間をかけすぎないで、次に進もう」
といった**“戦略的に解いていいんだよ”というメッセージ**です。
終わったあとは、
- 点数ではなく、最後まで一人で受けきったことをほめる
ようにしていました。
これを続けておくと、たとえ別の塾テストや模試を受けるときも、**「テストはこわくない」**という感覚で臨めます。
まとめ|全統小で平均以上(偏差値50以上)+テスト慣れがあれば、合格は十分狙える
最後に、ポイントを整理します。
- グノーブル小3入塾テストは
算数・国語の2科目/各100点、合計200点満点 - 内容は
- 基本計算・漢字
- 標準的な文章題
- 思考力・記述問題
がバランスよく出題される
- 体感難易度は全統小より一段階重い
- わが家の受験回では、合格ラインは75点以上で、長男もこれを上回る点数で合格
- 目安としては
全統小で“平均点以上”(偏差値50以上)なら、合格圏に入る可能性は高い - ただし、
- テスト慣れがない
- 時間配分が分からない
といった要因で、実力を出しきれずに落ちるケースもあり得る
- 対策の優先度は
- 全統小などでテスト慣れをしておく
- チャレンジタッチなどで基礎~標準レベルを取りこぼさない力をつける
- RISU算数・考える力プラスなどで思考力・図形・条件整理に触れておく
- 国語の記述は「枠を埋める」「部分点を取りに行く」感覚を身につける
グノーブルは、「考えることが好きな子」を伸ばしていくタイプの塾です。
グノーブル入塾テストそのもののイメージがついてきたら、
「うちの子にこの塾が合いそうか?」という視点で、塾の雰囲気もチェックしてみると安心です。
少人数クラスの様子や、プリント教材・各教科の方針などは
別記事の説明会レポに詳しくまとめました。
→ グノーブル説明会レポ|少人数クラス・教材・入塾テスト前に知っておきたいこと
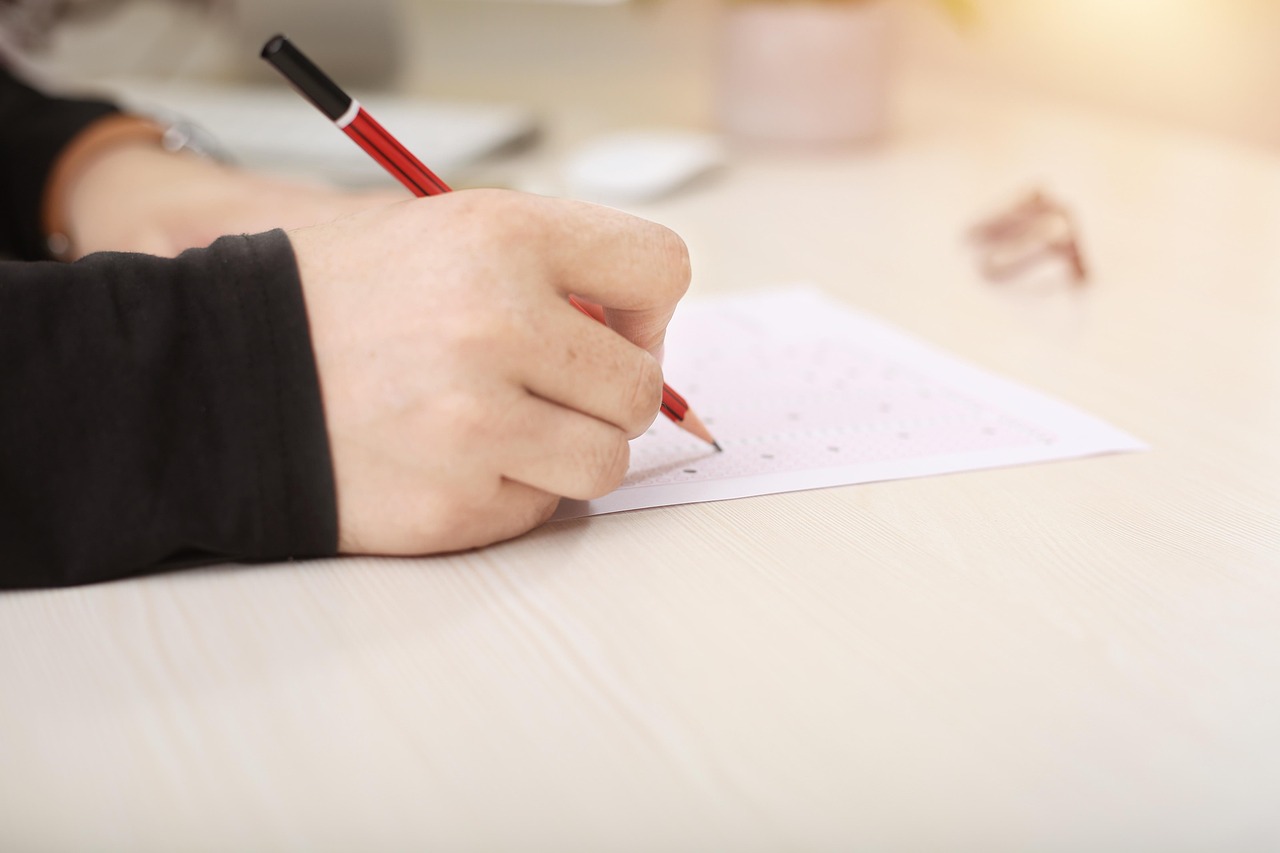

コメント